
取るだけ育休にしないための、過ごし方が知りたいな?
旦那さんが育休を取るとき、「どう過ごしたらいいの?」と悩みますよね。
育休中はママの気持ちに寄り添い、積極的に家事と育児を分担することが大切です!
育休は夫婦が協力し合いながら、新しい家族の絆を深める絶好のチャンスですよ♪
産後のママの身体は全治1~2カ月の交通事故並みのダメージを受けていると言われています…。
旦那としての役割を果たしつつ、育児はもちろん、家事やサポートなど、ママに喜ばれる過ごし方がしたいですよね。
さらに、旦那さんが育休中の給料事情や、家計への影響も気になるところ。
この記事では、パパとママの役割分担や、ママが助かる家事や育児はなにか、育休中の給料事情ついて詳しく紹介します。
旦那さんの育休を有意義な過ごし方にするために、ぜひ参考にしてくださいね!
パパの育休に役立つ便利グッズを紹介します♪
抱っこ紐で大人気のエルゴは、腰のパットがあるため、腰への負担が少なくなり、抱っこの安定感抜群なんですよ。
色も選べるので、パパと一緒に使っても違和感なく使えますよ!
旦那さんの育休中の過ごし方は?ママとパパで役割分担を決めよう!


旦那さんが育休を取ったけど、なにをすればいいのかわからない…。
旦那さんの育休中の過ごし方は、最初に無理なくできる役割分担を、話し合って決めましょう。
- 赤ちゃんのお世話担当の分担
- 家事の分担
- 夜間対応の分担
- 外出や手続きの分担
- メンタルケアの分担
育休の過ごし方は、育児も家事も頑張りたいけれど、旦那さんはどこまで手を出せばいいのか迷いますよね。
そんなときは、お互いの得意なことを活かしながら、無理なくママとパパで役割分担を決めるのが大切ですよ♪
パパとママができる具体的な役割分担を5つ紹介します。
おむつ交換など赤ちゃんのお世話担当を分担しよう
赤ちゃんのお世話は、ママとパパでバランスよく分担しましょう!

おむつ替え、ミルク作り、沐浴など赤ちゃんのお世話を積極的にするね!

授乳や赤ちゃんの体調管理を中心に担当するね!
例えば、パパはおむつ替えやミルク作り、沐浴など、赤ちゃんと触れ合えるお世話を担当するのがおすすめです。
しっかり触れ合うことでパパは育児に自信がつき、赤ちゃんとの絆も深まりますよ。
ママは授乳や赤ちゃんの体調管理など、細かいケアを中心にすると、お互いの役割分担ができます。
片方に負担がかからないよう、そのつど話し合って、柔軟に過ごし方を変更していけば、少しづつ慣れていきますよ♪
ゴミ出しなど家事の分担をしよう
育児と家事の両立は負担が増えるので、ママとパパで無理なく分担しましょう。

掃除、ゴミ出し、買い物など体力を使う家事は任せてね!

料理や洗濯物の畳みなど、日常の家事を担当するね!
パパは掃除、ゴミ出し、買い物など、体力が必要な家事を担当すると、ママの負担が軽くなります。
ママは料理や洗濯物の畳みなど、赤ちゃんを見守りながらできる家事を中心にするのがスムーズです。
ここで洗濯物の干し方や掃除の手順など、細かい部分で意見が合わないと、ストレスを感じます。
そんな時はやり方に違いがあっても、指摘しないで、「やってくれてありがとう」と感謝を伝えると、相手はやる気がアップするんですよ♪
子育てに慣れるまでは気楽に、「できる方がやる」と柔軟に対応すると、無理なく快適な過ごし方ができますよ。
夜中のミルクや夜間対応の分担をしよう
夜間の育児は寝不足になりやすく大変ですが、パパとママで分担するとお互いの負担が軽くなります。

夜中のミルクや寝かしつけを交代制でやっていこう!

授乳や体調不良の時のケアも対応するね!
育休中はパパがミルクの準備や寝かしつけなど、夜間の赤ちゃんのケアを積極的に担当することをおすすめします。
仕事に戻る予定のパパは、仕事復帰後に夜間の育児が厳しくなります。
交代制で対応時間を決めておけば、睡眠不足が解消され、パパも育児に積極的に参加しやすくなりますよ♪
夜間の赤ちゃんのケアをうまく分担できると、育児のストレスを減らすことができます。
役所の手続きや外出の分担をしよう
育児中は外出や手続きが増えがちですが、パパとママで情報共有して分担することが大切です。

役所の手続きや買い物を担当してママの負担を軽減するぞ!

予防接種などのスケジュール管理をして、予定を把握しておこう。
例えば、健康保険や育児休業給付金の申請、赤ちゃんの予防接種のための通院などがあります。
平日の日中に済ますことが多いので、パパが運転をしたり、役所の手続きをしたりするとママの負担が減ります。
でも初めての手続きや書類は複雑でミスしやすく、再度手続きをし直す事もあるので、ママも任せっきりはやめましょう。
ママは病院や赤ちゃんの定期健診、日々のスケジュールをスマホで管理をして旦那さんと共有すると、ミスが防げますよ♪
一人の時間を作るなどメンタルケアの分担をしよう
慣れない育児中は心身ともに疲れやすいため、メンタルケアの分担をしましょう。

ママが一人でリフレッシュできる時間を作ってあげよう!

パパの頑張りを認めて、意識して感謝の気持ちを伝えよう!
パパは赤ちゃんのお世話を積極的に担当したり、家事を手伝ったりすることで、ママが安心して一人の時間を持てるようになります。
ママはパパを労わり、感謝の気持ちを伝えることが、パパの育児へのモチベーションに繋がります。
育児に疲れたなと思った時は、シッターさんなど第三者の手を借り、2人の時間を作ることでリフレッシュもできますよ♪
一番大切なのはお互いに「ありがとう」と感謝の言葉を掛け合うことで、精神的なストレスは軽くなりますよ。
旦那さん育休中のパパとしての役目は?ママが喜ぶ家事育児を5つ紹介♪


ママが喜ぶ家事や育児が知りたいな?
旦那さんの育休の過ごし方でママが喜ぶ家事や育児は、おむつ替えなど5つあります。
- おむつ替え
- ミルク作り
- 沐浴
- 寝かしつけ
- 家事の分担
旦那さんが育休を取ったら、パパとして積極的に育児に関わることで、ママの負担が軽減されます。
パパができる、ママが喜ぶ家事や育児の役割を5つ紹介しますので、できることから始めてみてくださいね。
赤ちゃんのおむつ替えをしよう
パパが積極的におむつ替えをすることで、ママは他のことに手が回り負担が減ります。
おむつ替えは1日に何度も必要なため、育休中はママが食事中や入浴中、夜などにパパが対応すると、ママは自分の時間を持つことができます。
おむつ替えの際は、優しく声をかけたり、笑顔で接したりすると、赤ちゃんも安心しますよ。
慣れないうちは戸惑うかもしれませんが、回数を重ねるごとにスムーズにできるようになります。
赤ちゃんとのコミュニケーションの時間にもなるので、パパとしての自信をつけていきましょう。
ミルク作りを覚えよう
ミルク作りは正確な分量と適切な温度が大切です。
ミルク作りの手順に慣れるまでは、事前に確認しておくと安心です。
特に夜間のミルク対応は、パパが担当することでママの睡眠時間を確保でき、体調管理の助けにもなります。
ミルクを飲ませた後は、ゲップをさせてあげないと、赤ちゃんは不快になります。
ミルク後のゲップを優しく誘導すると、赤ちゃんの不快感を防げますよ。
慣れたらスムーズにできるようになるので、旦那さんが積極的に関わり、頼れる存在になりましょう。
沐浴からお着替えまでできるようになろう
沐浴をする際は、赤ちゃんの洋服を脱がすところから、お着替えまでできるようになりましょう。
パパが先にお風呂に入り、「赤ちゃんつれてきて~」とママを呼び、「出たよ~」とまたママを呼ぶことは、ママの本音としては嬉しくありません。
赤ちゃんの洋服を脱がし、沐浴して、体を拭き、保湿剤を塗って、洋服を着せるまでを1人でできるようになりましょう。
この時間で、ママは洗い物を終わらせたり、少しでもホッとしたりする過ごし方ができますよ。
寝かしつけをしよう
パパが育休中に寝かしつけを積極的にすることで、ママの負担が減ります。
優しくトントンしたり、子守唄を歌ったり、絵本を読むなど、赤ちゃんがリラックスできる方法を見つけましょう。
抱っこで寝かしつける場合は、背中スイッチ(置くと起きてしまう現象)に注意し、ゆっくり布団に降ろすと成功しやすくなります。
パパが寝かしつけを担当することで、ママがゆっくり休める過ごし方ができます。
家事の分担をしよう
パパが積極的に家事を担当することで、ママの精神的な負担も軽減されます。
掃除、洗濯、食事の準備は毎日必要な家事なので、得意なことだけでも手伝うと助かります。
例えば、洗濯物を干すのはパパ、畳むのはママなど、食器洗いやゴミ捨てなどすぐにできる家事はパパが行うと、ママの負担がぐっと減ります。
家事分担のポイントは、「手伝う」ではなく「一緒にやる」意識を持つことです。
旦那さんの育休中の給料は?お金にまつわる3つのことを紹介!


旦那さんの育休中のお給料のことが知りたいな?
旦那さんの育休中は制度を正しく理解して、節約を心がける過ごし方をしましょう。
- 育児休業給付金の受給額
- 社会保険料が免除される
- 節約と育休中の家計管理をする
旦那さんが育休を取るときに気になるのが「給料やお金のこと」ですよね。
収入が減るのではと心配する方も多いですが、制度を正しく理解し、計画的に準備すれば安心して育休を過ごせます。
こ育休中のお金にまつわる3つのポイントを詳しく紹介します。
育児休業給付金の受給額を知ろう
育児休業給付金は、育休中の収入減を補うために支給される制度です。
支給額は、育休開始から6カ月までは休業前の給料の67%、それ以降は50%が受け取れます。
申請は勤務先を通じて行い、振り込みは2カ月ごとです。
受給には条件があり、育休取得前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上あることが必要なので、事前に確認しておくと安心です。
育休を計画する際は、この給付金をうまく活用し、家計の見直しも合わせて行いましょう。
育休中は社会保険料が免除される
育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の支払いが免除される。
免除期間中も年金の加入期間としてカウントされるため、将来の年金額が減る心配もありません。
収入は減るものの、社会保険料の負担がなくなるため、育児休業給付金とあわせると、手取りは抑えられます。
育休取得を検討している場合は、この制度を活用して、家計の負担を軽くしながら安心して育児に専念しましょう。
節約と育休中の家計管理をする
育休中は収入が減るため、節約と家計管理がとても重要になります。
まずは、固定費(家賃・通信費・保険など)を削減できないかチェックしましょう。
例えば、スマホを格安SIMに変更するだけでも節約効果は大きいですよ。
さらに、自治体の子育て支援制度の助成金や無料サービスを活用すると、育児費用を抑えられます。
育休中は収入が減る分、「どこを節約できるか」夫婦で話し合い、計画的に家計を管理しましょう。
まとめ

- 旦那さんの育休中の過ごし方は、最初に無理なくできる役割分担を、話し合って決める。
- 旦那さんの育休の過ごし方でママが喜ぶ家事や育児は、おむつ替えなど5つある。
- 旦那さんの育休中は制度を正しく理解して、節約を心がける過ごし方をしよう。
旦那さんの育休中は、夫婦で役割分担を決め、協力しながら育児と家事をこなすことが大切です。
育児休業給付金や社会保険料の免除制度を活用すれば、収入減の不安を軽減できます。
育休は、パパにとっても赤ちゃんと深く関わる貴重な時間なので、夫婦で支え合いながら、充実した育休生活を送りましょう!
エルゴベビーは、パパでも楽に抱っこできる設計になっており、育児をサポートする心強いアイテム。
「抱っこ=ママの役目」ではなく、パパも積極的に関わることで、育児の負担を分担できるだけでなく、赤ちゃんとの絆も深められます。
エルゴベビーを活用して、パパも育児を楽しみましょう!

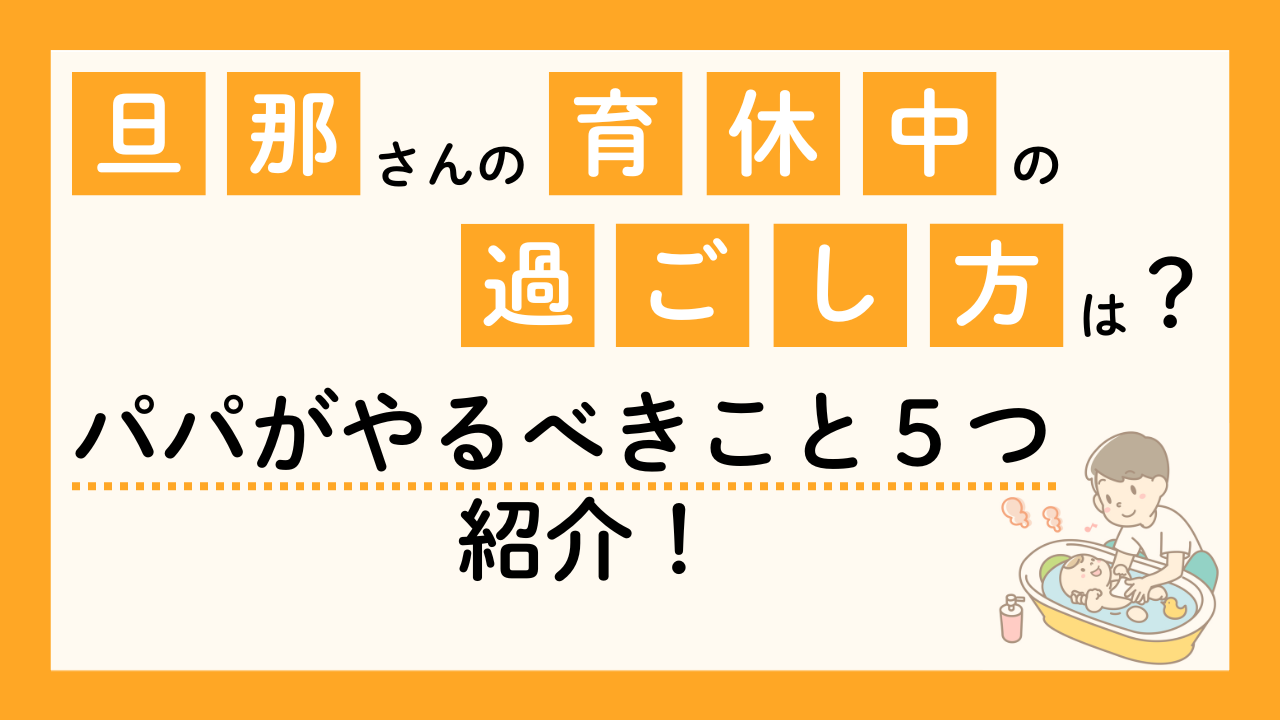
コメント