
エコー写真が消えない保存方法を知りたいな!
エコー写真は保存方法を工夫することで、消えないようにすることができます!
エコー写真は産婦人科の妊婦検診の時にもらうことが多いかと思います。
ある時、エコー写真を見返してみると画像が薄くなっていたり、消えてしまっていたり、あるいは真っ黒くなっていたり、という経験をされた方もいるのではないでしょうか?
エコー写真は感熱紙を使用しているので、保存方法が適切でないと画像が薄くなったり、消えてしまったり、あるいは真っ黒くなってしまうことがあるんです。
赤ちゃんの成長を感じられるエコー写真が消えないようにするには、保存方法が重要になります!
この記事ではエコー写真の保存方法を工夫して、赤ちゃんの成長を感じられる大切な思い出が消えないようにする対策をご紹介します♪
赤ちゃんの成長を感じられるエコー写真を保存するために、「エコー写真専用のアルバム」を用意しませんか?
かわいい台紙にコメントが付いていて、エコー写真を貼るだけで絵本のようになり、エコー写真を一冊のアルバムに残せます。
ママ・パパからのメッセージを書き込めるスペースもあり、世界にひとつだけのオリジナルのエコー写真アルバムを作ることができます!
エコー写真は保存方法を工夫すれば消えない!感熱紙の特徴と注意点

エコー写真は感熱紙といわれる特殊な紙を使用しており、保存方法が適切でないと画像が薄くなったり、消えてしまったり、あるいは真っ黒くなったりしてしまうことがあるんです。

エコー写真の保存方法で知っておいた方がいいことって何があるのかな?
- エコー写真の原本の保存方法は?
- エコー写真の保存方法を工夫して消えないように!おすすめ対策は「データ化」
- 知っておきたい感熱紙の特徴
- 知っておきたい感熱紙の注意点
赤ちゃんの成長を感じられるエコー写真が、薄くなったり、消えてしまったり、あるいは真っ黒くなっってしまっては、とても悲しいですよね。
でも大丈夫!
エコー写真は保存方法を工夫することで、消えないようにすることができます!
ここでは、エコー写真の原本の保存方法と、保存方法で知っておきたい基礎知識をご紹介します。
エコー写真の保存方法で知っておきたい基礎知識をもとに、保存方法を工夫して、赤ちゃんの成長を感じられるエコー写真が消えないように対策をしましょう!
1:エコー写真の原本の保存方法は?
エコー写真の原本の保存方法は、保存環境に配慮することが大切です。

エコー写真の原本の保存方法はどうしたらいいのかな?
エコー写真の原本の保存方法を詳しく見ていきましょう。
- 直射日光や高温多湿な場所を避け、冷暗所に保管する
- 熱の影響を受けるので、暖房器具の近くには保管しない
- 薬品や除光液の近く、水回りには保管しない
- 摩擦を避けるため、エコー写真を折ったり、エコー写真どうしが重なったりしないように注意する
エコー写真の原本は時間の経過とともに、薄くなったり、消えてしまったりします。
将来的にエコー写真の原本が薄くなったり、消えてしまったりすることは避けられません。
しかし、保存方法や保存環境に配慮することで、少しでも長くエコー写真の原本を保管しておくことは可能になります。
上記のエコー写真の原本の保存方法を参考に、保存環境に配慮して、大切なエコー写真の原本を少しでも長く保管できるようにしましょう!
2:エコー写真の保存方法を工夫して消えないように!おすすめ対策は「データ化」
エコー写真の保存方法を工夫して消えないようにするには、「エコー写真をデータ化する」のがおすすめです!

エコー写真をデータ化するには、どうしたらいいのかな?
エコー写真をデータ化するには、3つのステップがあります。
- エコー写真をアプリでスキャンする
- スキャンしたものをプリンターでプリントする
- プリントしたものをアルバムに保存する
使うアイテムは「アプリ」と「プリンター」と「アルバム」です。
私たちの身近なアイテムを使ってエコー写真をデータ化することで、消えないように対策することが可能になります。
エコー写真をデータ化する作業は上記のアイテムを使えば、それほど難しいことはありません。
検診ごとに、エコー写真をコツコツとデータ化していけば作業時間もあまりかかりませんよ。
3:知っておきたい感熱紙の特徴
感熱紙の一番の特徴は、「熱によって発色する」ということです。

エコー写真に使われてる感熱紙って、どんな特徴があるのかな?
感熱紙の特徴を詳しく見ていきましょう。
- 紙の表面に専用の薬品が塗られている
- 紙の表面に熱を加え、表面の薬品と熱が化学反応を起こすことで色が変化し、黒く発色することで画像の印刷や印字ができる
- プリンターを使用せずに印刷が可能
- 熱を加えて印字することで、高速で印字・印刷ができる
私たちの身近なものにも感熱紙は使われていて、レシートやチケット、ラベルなどに広く使われています。
時間が限られている妊婦検診では、「熱を加えて印字することで、高速で印字・印刷ができる」という部分が、感熱紙が使われるメリットなのではないでしょうか。
4:知っておきたい感熱紙の注意点
感熱紙の注意点は、保存方法や取り扱い方法を誤ると、印字が薄くなったり、消えてしまったり、黒くなったりしてしまうことです。

感熱紙の注意点を教えて!
感熱紙の注意点を詳しくみていきましょう。
- 温度や湿度の変化、日光に弱い
- 薬品や除光液が付着したり、水で濡れてしまったりすると、印字が滲んだり、消えたりすることがある
- 摩擦によって画像・印字が薄くなることがある
- 数ヶ月~数年で画像・印字が薄くなる可能性があるので、長期保存には不向き
感熱紙は、熱・高温に反応し、エコー写真が真っ黒になってしまいます。
検診後のエコー写真を誤って車内に置きっぱなしにしてしまうと、車内の温度が高くなることで、エコー写真が真っ黒になってしまうので、置忘れには気を付けて下さい。
感熱紙の注意点を知っておくことで、エコー写真の保存方法の工夫ができ、赤ちゃんの成長を感じられる大切な思い出が消えないようにすることができます。
エコー写真の保存方法にアプリを活用!おすすめ4つをご紹介♪

エコー写真をデータ化することで、アプリ内に保存することができ、長期保存に適した状態にすることができます。

エコー写真の保存方法に使える、おすすめのアプリはどんなものがあるのかな?
- エコー写真
- ALBUS(アルバス)
- フォトスキャン by Google フォト
- トツキトオカ
まずは、エコー写真をアプリでスキャンして、データ化していきましょう!
さらに、データ化したエコー写真を、プリンターで光沢紙を使用して印刷することで、写真にして保存方法を工夫することで、長期保存も可能になります。
それぞれのアプリの特徴を見ていきましょう。
おすすめアプリ1:エコー写真
「エコー写真」は名前の通り、エコー写真を保存するためのアプリです。
写真部分をトリミングしてスキャンできるので、エコー写真をキレイに保存できます。
アプリを起動してスキャンするだけなので、操作も直感的に簡単にできます。
スキャンした写真は、スマホの写真ホルダー内に「エコー写真」というタイトルで自動的にアルバムが作成され、保存されます。
また、エコー写真では、妊娠週数と撮影日を記録することができるのが嬉しいポイント!
あとから画像を見ても、いつ頃のエコー写真なのかすぐに分かります。
おすすめアプリ2:ALBUS(アルバス)
「エコー写真」とセットで使いたいアプリです。
「ALBUS(アルバス)」は、「エコー写真」と連携することが可能で、毎月8枚まで無料で写真をプリントすることができるアプリなんです。
アプリからプリントしたい写真を選び、注文ができるので、スマートフォンに取り込んだエコー写真を簡単にプリントできます。
写真のサイズは8.9×8.9㎝の正方形のましかくで、白フチのあり・なしを選択できます。
おすすめアプリ3:フォトスキャン by Google フォト
「フォトスキャン by Google フォト」はGoogleが開発した写真スキャンアプリです。
エコー写真の四隅にカーソルを合わせるだけで、簡単にスキャンできます。
スキャンした画像は、自動的にスマートフォンに保存されます。
また、Googleフォトアプリにもバックアップできるので、パソコン管理も可能になります。
自動補正機能があるので、エコー写真をスキャンする時に入り込む光や影、歪みを自動補正し、光や影が映らないきれいな状態で取り込むことができます。
おすすめアプリ4:トツキトオカ
「トツキトオカ」は妊娠記録・妊娠日記が主な機能のアプリです。
このアプリのみで、日々の体調や検診結果を記録することができ、さらに検診でのエコー写真も一緒に保存することができるんです!
トツキトオカに記録したエコー写真は毎回9枚まで印刷が無料なのも魅力的です。
トツキトオカは夫婦でアプリを共有することができます。
検診後、エコー写真をアプリに保存することで、検診に立ち会えなかったパパともタイムリーにエコー写真を共有することができます。
私も、妊娠中にこのアプリを使っていて、検診に来れなかった主人とエコー写真も共有していました。
今も、時々アプリを開いて、妊娠中の記録やエコー写真を眺めて「懐かしな」と思い出に浸っています!
エコー写真の保存方法に無印のアルバムを活用!おすすめ3つをご紹介♪

エコー写真をデータ化し、プリントしたあとに使用するアルバムは無印良品のアルバムがおすすめです!

エコー写真の保存方法に合った、無印良品のおすすめのアルバムを教えて!
- 無印良品 ポリプロピレンアルバム3段 スクエアサイズ・240枚用
- 無印良品 ポリプロピレンアルバム L判・264枚用
- 無印良品 ハードカバーアルバム KGサイズ2段・20ページ
エコー写真をアプリでスキャンしてデータ化し、そのデータを写真としてプリントしたあとの保存方法として、アルバムが必要になります。
無印良品は実店舗が多く、実際のアルバムを手に取って確認して購入することができます。
また、お値段も良心的でお財布にも優しく、「お試しで使ってみよう!」ということも可能です。
アルバムの種類も多く、あなたのエコー写真の保存方法に合った、アルバムが見つかると思いますよ!
それぞれのアルバムの特徴をご紹介します。
おすすめ1:無印良品 ポリプロピレンアルバム3段 スクエアサイズ・240枚用
8.9×8.9㎝のスクエアサイズ用のフォトアルバムです。
サイドインの収納方法で、簡単に写真を出し入れすることができます。
240ポケットあり、データ化したエコー写真のみならず、マタニティフォトや産まれたあとの子どもの写真も一緒に保存できます。
大容量なのにアルバム1冊のお値段は、450円でコストパフォーマンスもとっても良いです。
「もう少し容量が少なくてもいいかも」という方は、無印良品の同じスクエアサイズのアルバムで、216枚用のアルバムもあるので、そちらもチェックしてみて下さい。
おすすめ2:無印良品 ポリプロピレンアルバム L判・264枚用
一般的なL判サイズの写真を収納できるアルバムです。
こちらも、サイドインの収納方法で、簡単に写真を出し入れすることができます。
こちらは、多目的用ポケットも付いているので、命名書やママやパパからのメッセージカードなども一緒に保管できます。
L判写真を264枚収納できる大容量アルバムなので、こちらもエコー写真のみならず、マタニティフォトや産まれたあとの子どもの写真も一緒に保存できます。
アルバム1冊のお値段は590円と、こちらも良心的なコストパフォーマンスです。
おすすめ3:無印良品 ハードカバーアルバム KGサイズ2段・20ページ
こちらは、ハードカバータイプのアルバムで無印良品の良さであるシンプルさもあり、かつ高みえ感もあるアルバムです。
カラーもグレーとベージュの2色展開なので、お好みのカラーを選んだり、収納するお部屋の雰囲気に合ったカラーを選んだりすることもできます。
アルバム1冊のお値段は990円ですが、ハードカバータイプのアルバムが1,000円以下で買えるのは無印良品さんだからではないでしょうか。
同じハードカバータイプのアルバムで、写真を1ページに1枚ずつ収納できる1段タイプのアルバムもあるので、気になる方はそちらもチェックしてみて下さい。
まとめ

- エコー写真の感熱紙の特徴と注意点を知って、エコー写真が消えないように保存方法を工夫し、保存環境に配慮して保管することが大切。
- エコー写真をアプリでスキャンしてデータ化し、プリントして写真として保管することでエコー写真が消えないように保存することができる。
- プリントした写真のエコー写真の保存には、無印良品のアルバムがコストパフォーマンスも良く、おすすめ。
エコー写真は、感熱紙の特徴や注意点を理解し、保存方法や保存環境に配慮することが大切です。
さらに、エコー写真をアプリを使ってデータ化することで、アプリ内で保存したり、写真として残したりすることができます。
ぜひ、この記事を参考にしていただき、エコー写真の保存方法を工夫して、赤ちゃんの成長を感じられる大切な思い出が消えないように対策をしてみて下さい♪
赤ちゃんの成長を感じられる大切な思い出が消えないように、「エコー写真専用のアルバム」を用意しませんか?
命名紙や手形・足形も一緒に残すことができ、世界にひとつだけのオリジナルのエコー写真アルバムを作ることができます!
子どもが大きくなってから、家族で一緒にこのエコー写真アルバムを見返すことで、家族の絆をより深めることができますよ。

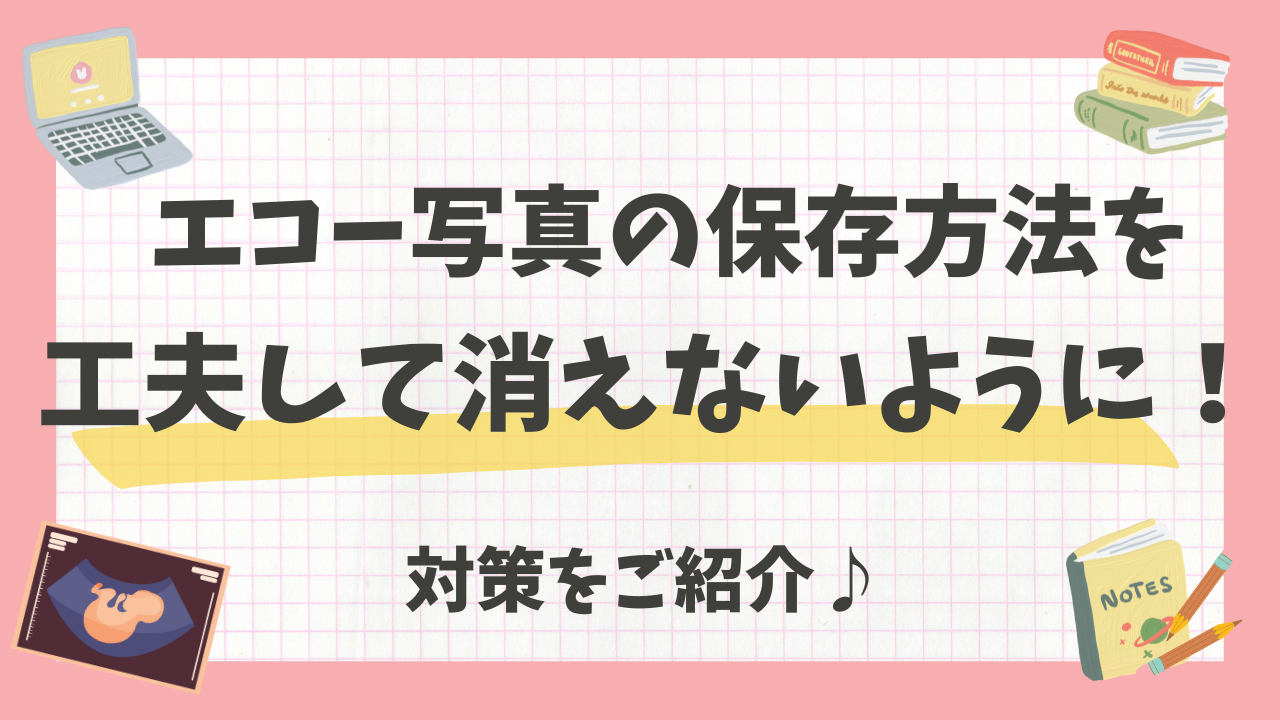

コメント