子どもの成長を祝う大切な行事である七五三は、女の子が3歳と7歳で、男の子が3歳と5歳で行うのが一般的です。
晴れ着である振袖や袴を身につけた姿は、とても可愛らしく、カッコいい姿で、親としては成長を感じられ嬉しくなりますよね♪
七五三の晴れ着姿は、特別な記念としてフォトスタジオで写真撮影をする親御さんも多いです。
七五三の晴れ着は、子どもの成長を願い大きいサイズで準備する方もいらっしゃいます。
せっかく準備した晴れ着を可愛らしく、カッコよく着るためには「腰上げ」という事前の準備が大切です!
この記事では、「腰上げの基本的な知識」と「腰上げの簡単な方法」をご紹介します。
ぜひ、この記事で腰上げの簡単な方法を知ることで、ママも子どもも負担を軽くして、特別な日を楽しむことができますよ♪
七五三でママが行う事前準備の一つ、「腰上げ」の負担を軽くしませんか?
着物の腰上げの負担を軽くするのに、布用両面テープを使って腰上げをするのがおすすめです!
アイロンも不要なのが嬉しいポイントです♪
七五三の腰上げは簡単にできる?基本的な知識とメリットとデメリット


七五三の腰上げって簡単に家でもできるのかな?

腰上げはご家庭でもできます!まずは腰上げの基本的な知識を確認しましょう!
七五三の腰上げはご家庭でもでき、特に和裁や洋裁の経験がある方なら簡単にできるものです。
腰上げは、着物の着崩れを防ぎ、子どもが活動しやすくするための作業になります。
この記事ではまず、「腰上げ」の基本的な知識を確認していきましょう!
腰上げの具体的な手順を紹介!
腰上げとは、七五三の着物の腰の部分をつまみ上げて縫い、着物の丈を子どもの身長に合わせて調節する事です。
腰上げの手順を簡単にご紹介します。
- 着丈を測る:子どもにまっすぐ立ってもらい、首の付け根(首のぐりぐり)から足のくるぶしまでの長さを測る
- 腰上げの位置を決める:着物の身丈から、測った着丈の長さを引いて、余った長さを縫い上げる
- 縫い付ける:余った部分を布がずれないように、着物の裏側に折りたたんで、数か所を手縫いで縫う
※着丈:子どもが実際に着用する際の長さで、首の付け根から足のくるぶしまでを指す
※身丈:着物本来の長さで、着物の襟から裾までの長さを指す
大人の場合は腰ひもを使用して腰上げをしますが、子どもは激しい動きをするので腰ひもだけの腰上げでは着崩れてしまいます。
そのため子どもの場合は、着崩れを防ぐ目的で縫って腰上げをするのが一般的です。
「自分で腰上げをやってみよう!」という方は、「七五三 腰上げ 縫い方」で検索してみて下さい。
腰上げの縫い方を紹介しているサイトや動画が見られるので、参考にしてみて下さい。
腰上げのメリット・デメリットと腰上げがおすすめなシーン
腰上げにはメリット・デメリットがそれぞれあり、また腰上げするのがおすすめなシーンがあります。
腰上げのメリットとデメリット、腰上げがおすすめなシーンを詳しくを見ていきましょう。
- 着付けの時間が短くなる
- 着付けの際に腰ひもで締め付ける必要がないので、子どもの機嫌が悪くならない
- 動き回っても着崩れしにくくなる
特に3歳前後の場合は、着物の着用で行動を制限してしまうとご機嫌が悪くなってしまいます。
そのため、元気いっぱいに動き回っても着崩れしないよう、大丈夫なように腰上げをしておくのをおすすめします!
- 自分でする場合、時間と手間がかかる
- 専門店へ依頼した場合、料金がかかる
「時間と手間をかける」か「お金をかけるか」を検討し、ママの負担にならない方法を選択すると良いかと思います。
- 着物を着た状態で、半日~1日中お出かけをする場合
- 2~3歳の小さい子どもの場合
神社への参拝時や写真撮影でロケーション撮影をする場合は外出時間も長くなり、着物の着用時間も長くなります。
着慣れない着物でのお出かけは、子どもにもママにも精神的・身体的負担が大きくなってしまうことも……。
子どもの活発な動きで、せっかくの着物が着崩れしてしまったり、裾を踏んで転んでしまったりすることもあります。
七五三という特別なイベントを楽しく、穏やかに過ごすためには、事前の準備で腰上げをしておくと安心ですね♪
七五三の腰上げ3歳はどうする?被布でカバーして可愛らしさもアップ!


3歳の子どもの腰上げ、自分で縫ってみようと思うんだけど上手く縫えるか心配……

3歳の七五三の腰上げは上手く縫えていなくても心配ありません!
3歳の七五三では、着物の上に着用する「被布」で腰上げ部分がカバーされるので、上手く縫えていなくても心配ありません!
3歳の七五三は「女の子のお祝い」というイメージを持つ方も多いですが、地域によっては男の子も3歳の七五三のお祝いをします。
また、七五三のお祝いをする年齢や性別には厳密な決まりがなく、最近は男の子がお祝いすることも増えてきました。
被布は、年齢や性別に関係なく着用できるので、3歳の男の子の七五三でも袴ではなく被布を選択する方も多いです。
腰上げ部分をカバーできる「被布」とはどのような物なのか、見ていきましょう。
被布とは?着用するメリットをご紹介!
「被布」とは、着物の上に着用する丈の短い羽織物で、袖が無く、えりもとは四角く空いたデザインになっています。
被布は、帯を締めない年齢である3歳の七五三で着用するのが一般的です。
被布は、ベストのような形をしていて、おなか回りがすっぽりと隠れるデザインなので、腰上げ部分もしっかりとカバーしてくれますよ♪
- は、おなか回りの締め付けが少なく動きやすいので、子どもへの負担が少ない
- 被布は、着るのに複雑な工程がないため、気軽に着付けができる。トイレや休憩の際も、着物の乱れを過度に心配する必要がなく、万が一着崩れしても簡単に直せる
- 被布の丸みを帯びたシルエットが、3歳ならではの可愛らしい印象を引き出し、この時期の子ども特有の柔らかさやあどけなさといった特別な魅力を発揮できる
被布の選び方は?ポイントは成長への願いと全体的な統一感
被布は色柄のデザインが豊富なので、子どもに似合うだけでなく、柄の意味を知っておくと選びやすくなりますよ♪
3歳の七五三で着用する被布の選び方のポイントを押さえて、子どもに合った被布を選びましょう。
素敵な衣装を用意することで、気持ちが盛り上がり、より一層楽しく七五三に参加できますよ!
【着物との柄のバランスを調整する】
柄が多い着物を着る場合は、シンプルな無地の被布がおすすめです。着物の邪魔にならず、全体のバランスが整います。また、逆に着物の柄が少ないときは、柄の入った被布を選ぶことで、華やかな印象を演出できます。
なお、着物の柄にはそれぞれ意味があり、代表的な柄が持つ意味は、以下の通りです。
| 着物の柄 | 意味・願い |
| 【男の子】兜(かぶと) | 邪気や災難から守られますように |
| 【男の子】宝船(たからぶね) | 一生、物に困ることがないように |
| 【男の子】鷹(たか) | 先を見通す力が付きますように |
| 【女の子】鞠(まり) | 何事も円満に進みますように |
| 【女の子】鈴(すず) | 邪気から身を守り良縁に結ばれますように |
| 【女の子】糸巻き(いとまき) | 健康的に長生きできますように |
【全体的な統一感を重視する】
被布は着物の上から重ねて着るため、着物に合う色を選ぶことが大切です。同系色で上品にまとめる方法や、反対色を選んで個性的に仕上げる方法などいくつかのパターンがあります。
着物と被布のおすすめの組み合わせは、以下の通りです。
| 【同系色の組み合わせ】 | 【反対色の組み合わせ】 |
| 赤×薄ピンク | 水色×薄ピンク |
| オレンジ×赤 | 青×赤 |
| 黄色×白 | 黒×白 |
| ピンク×白 | |
| 水色×白 | |
| 黒×水色 | |
| 緑×白 | |
| 青×水色 |
コーディネートが難しい時は、白の被布を選ぶと、どの色・柄の着物にも馴染みやすく、落ち着いた印象になりますよ♪
七五三の腰上げは縫わない方法もある!ママの負担を軽くしよう!


七五三の着物を縫わないで、腰上げができる方法ってあるのかな?

七五三の着物を縫わないで、腰上げができる方法もありますよ♪
七五三の着物を縫わないで、腰上げができる方法もあります!
- おはしょり(お端折)をする
- 両面テープを使う
- サスペンダーを使う
着物を縫うとなると、長さを測るためのメジャーや定規、縫うための針や糸などを用意する必要があります。
メジャーや針、糸などは100円ショップでも購入できますが、裁縫道具から用意するとなるとなかなか腰が重くなります。
私は、用意する道具、使用する道具はできるだけ少ない方が嬉しいです!
着物を縫わないで腰上げできる方法を、それぞれ詳しく見ていきましょう。
おはしょりは縫わずに子どもの体型に合わせて美しく着付けができる!
七五三で腰上げをしない場合は、おはしょり(お端折)で調整することで、縫わずに着付けが可能になります。
おはしょりとは、着物の丈を身長に合わせるために余分な丈を腰でたくし上げ、帯の下から見えるように折り返す部分のことを指します。
着物の裾の長さを調整する役割があり、特に女の子(女性)の着付けの際に行います。
おはしょりのメリット・デメリットを見ていきましょう。
- 手間と費用が省ける:腰上げの縫製作業や、専門店に依頼する費用を削減できる
- きれいに着付けられる:身長や体型に合わせておはしょりを調節できるため、美しく着付けられる
- 着付け時間が長くなる場合がある:子どもの体格に対して大きな着物の場合、おはしょりで調整するための時間が増え、着付けが負担になることがある
- 着崩れしやすくなることがある:縫っていない分、動きによって着崩れるリスクが高まるため、きつめの着付けが必要になる場合がある
- 子どもの負担が増える可能性がある:長時間着用する場合、きつく着付けなければならない状況もあり、腰回り・お腹回りが苦しくなったり、気分が悪くなったりなど子どもの負担が増えることがある
腰上げをおはしょりで対応するかは、子どもの体格および年齢や性格、着物を着用する状況や時間を考慮することがおすすめです。
裁縫が得意ではない方には両面テープがおすすめ!
裁縫が得意ではないという方やもっと簡単に腰上げをしたいという方は、両面テープを使って腰上げするのがおすすめです!
両面テープを使って腰上げする方法はいたってシンプルで、腰上げで縫い合わせる部分を両面テープで貼り合わせます。
両面テープで腰上げする場合は、「布用」と記載のある両面テープを使用して下さい。
「布用」ではない両面テープを使用してしまうと、粘着力が弱かったり、強かったりしてしまいます。
粘着力が弱いと、子どもの動きによって腰上げ部分がはがれてしまい着崩れしてしまうことも……。
粘着力が強いと、腰上げした部分がもとに戻せなくなってしまい、無理にはがそうとすると着物を傷めてしまうことも……。
両面テープで腰上げをする際は、購入する両面テープの種類を必ず確認してから購入して下さいね。
「両面テープでできるなら、私にもできそう」と感じたママ、ぜひチャレンジしてみて下さい!
男の子にはサスペンダーを使うのがおすすめ!
厳密な腰上げには当てはまりませんが、着物の裾の長さを調整するという意味では、子ども用サスペンダーを使うのもおすすめです!
5歳の男の子の七五三では、袴を着用しますが、履かせたこともなければ、普段さわったこともないとう方が多いと思います。
子どもはじっとしてはいないので、時間が経つとどんどん袴が下がってきて、裾をひきずるのではないかという心配も……。
そんな悩みを解消するために、袴をサスペンダーで吊ってしまうという着付けスタイルが多くなっています。
サスペンダーは子ども衣料品店や100円ショップにもあるので、比較的、準備はしやすいと思います。
男の子の七五三では、5歳は着物の上に羽織を着るので、サスペンダーをつけていても羽織でカバーされ、サスペンダーは見えないですよ!
まとめ

- 七五三の腰上げはご家庭でもでき、特に和裁や洋裁の経験がある方なら簡単にできる
- 3歳の七五三では、着物の上に着用する「被布」で腰上げ部分がカバーされるので、上手く縫えていなくても心配ない
- 両面テープやサスペンダーを使うことで、七五三の着物を縫わないで、腰上げができる方法もある
どの年齢の七五三も一生に一度しかなく、親子ともに楽しみで、大切にしたいイベントです。
ママが簡単な方法で腰上げができ、子どもは七五三の写真撮影やお参り当日を負担が少ない状態で臨めるのが理想的です。
ママが簡単かつ負担が少なく腰上げができるアイテムが色々ありますし、業者に依頼するのも一つの方法です。
各ご家庭で、ママも子どもも負担が少ない状態で七五三に臨めるよう上手にアイテムを活用し、楽しい七五三を迎えて下さいね♪
布用両面テープを使って腰上げするのが、簡単でおすすめです!
事前に腰上げを行っておくことで、七五三当日の子どもの負担を軽くすることができます。
両面テープで腰上げ後も洗濯ができるので、写真撮影後に汚れても心配ありません。

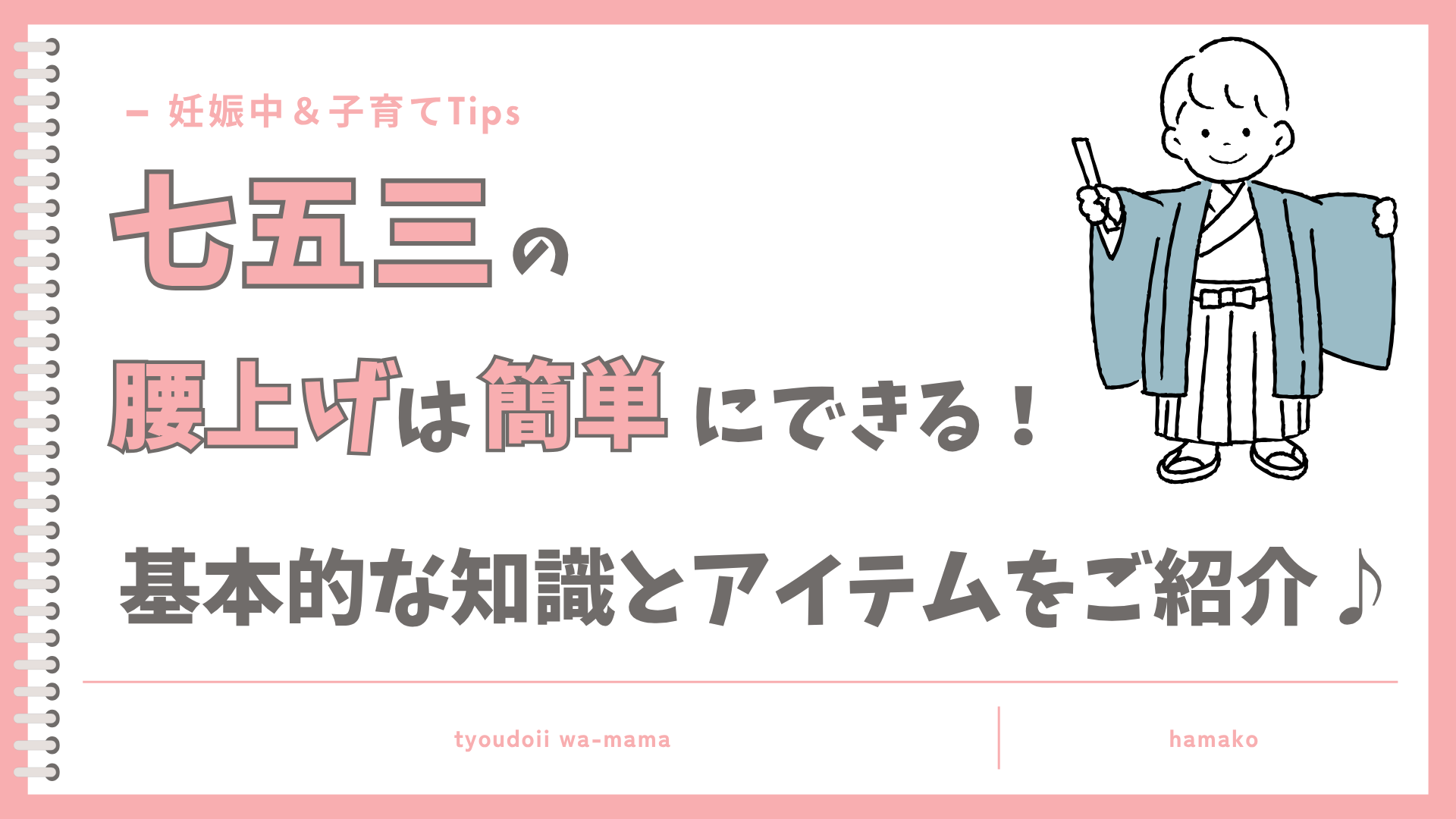


コメント